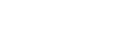骨太の農業を(ブログ4076)
- 2025年10月25日
1昨日、「北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会」が、農地の再編整備に関する要請を道議会の核会派に行いました。
資・肥料の高騰や燃費の高騰で厳しい営農を余儀なくされてきた農業も、近年やっと農地の「大区画化」や国内の需要に応じた作物の生産を可能とする「汎用化、排水改良」といった農業生産基盤整備事業が進み、地域が一体となって収益率を高め、農業の成長産業化を目指す機運が高まっている中、高市政権の鈴木農水相が、石破内閣での米の増産に水をかけるように「需要に応じた生産が必要だ」とか「政府が価格にコミットするべきではない」と話しています。
米不足に伴って備蓄米を放出したときは、米の市販価格は2,000円台でしたが、その後は3,000円台になり、今は新米が豊富にあっても4,000円台と高止まりとなっています。
物価高騰が収まらず、所得の低い方々は米を食べたくても手が出ないと嘆いていますが、鈴木農水相は、「それは、需要と供給だから仕方が無い、政府が対策を行う問題ではなく市場経済だ」と言わんばかりです。
昨年、農水省の判断の見誤りがあって、夏から米不足が始まりました。「食管法」が変遷して、米を生産者が自由に販売できる「食糧法」になりましたが、昨年からの米不足により、商社や中間卸売業者が農家との直接売買の量を増やすようになり、それも高値での取引で米を抱え込んだために、損をしないように市場へ出回る米価は、先ほどのように4,000円を超えています。つまり、昨年からの米不足は価格面から見ると何も解消されてはおりません。
鈴木農水相は、需要に応じた生産が必要だと話していますが、需要と供給の間には1年間のギャップが生じることをご存じなのか? リアルな需要と供給は農業には当てはまらず、過去の実績と、今後の予想を基にした営農計画の中で生産者は翌年度の生産目標を決定します。米不足を避けるためには需要を満たす多めの生産が必要で、余剰米は政府が買い入れて輸出に振り向けるという政策が不可欠です。
食糧自給率が相変わらず38%でしかない日本は、今後も農産品の増産を進めなければならないのは明らかです。
先ほどの農地拡大のための圃場整備で、多くの農家がやりがいを達成でき、収入も増え、休暇も取得することが出来、何より後継者を作り上げることが出来るようになりました。
鈴木農水相も、頭を切り替えて農政に力を入れて欲しいと思います。