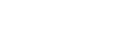関係人口(ブログ3943)
- 2025年06月14日
政府は、石破氏の看板政策として「地方創生2.0」の推進方策として、人口減少を前提とした上で、年と地方の住民が継続的に関わる「関係人口」に力を入れるようです。
石破氏は、「人口減を正面から受け止めた上で経済成長し、社会を機能させる適応策を講じる」とその考え方を示しました。
揚げ足を取るわけではありませんが、これまで人口減少を正面から受け止めていなかったと言うことなのでしょうか、1994年に政府は少子化と女性の社会進出に対応した「エンゼルプラン」を策定し、子育て支援などを行ってきましたが、その効果はほとんど無く、1999年には新たに「新エンゼルプラン」を策定しました。しかし、その効果も合計特殊出生率には表れず、プラン自体もしぼんでしまいました。
その後、効果的な政策を行わず、パッチワーク的な対応しか行ってこなかったせいで、少子化は右肩下がりを続けついに出生率が1.15までになってしまいました。
石破流に言うと、今まで正面から受け止めていなかったことが、今の状況を生んでいると言うことになります。
そこで、「人口減少は打つ手が無いから諦めた」とばかりに、「関係人口」に目を付けたということになります。
その街に住民票は無いけれど、何度か訪れているうちにそこの住民と仲良くなったとか、都会と田舎の二重生活を楽しみたいという方々などを「関係人口」と位置づけて、「ふるさと住民制度」を創設するとのことです。
つまり、住民票の無い方々を「ふるさと住民」として登録し、見せかけの人口とするという、姑息な考え方のような気がします。
過去に函館市の市長が「誰がどんな制度を作っても少子化に歯止めをかけることは不可能だ」したがって、「年間500万人の観光客(今年は606万人の入り込み)を1年間365日で割ると約13,700人だから、その分人口が増えたのと同じだ」というへんてこりんな理屈を用いたことがありました。
今度の「関係人口」も何か同じような気がします。
無論、都会の方々が地方と関係を強くしてくれることは、大歓迎ですが、それは「人口」とは関係が無い「交流」では無いでしょうか。ふるさと応援隊の方々には感謝しますし、それが移住につながればありがたい話ですが、それは単なる「移動」であってそのことで日本全体の人口減少が解決に向かうことにはなりません。問題は、少子化に歯止めをかける効果的な政策を総合的にどう具体化するかにかかっていると言うことです。
石破氏の「地方創生2.0」の本気度が試されます。