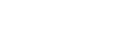避難と課題の検証(ブログ3990)
- 2025年07月31日
カムチャッカ地震から1日が過ぎました。
日本の太平洋岸一帯と日本海側の一部に出された津波警報は、津波注意報となり函館市民の生活も平常を取り戻しました。
昨日はマグニチュード(M)8.8と言われていましたが、実際にはM8.7に0.1ほど低下しましたが、それであっても最大級の地震であった事に代わりはありません。
今回の地震による津波警報の発令に伴って出された避難指示には、市民の多くが反応しましたが、以前から各家庭に配布されている「津波ハザードマップ」、河川氾濫による「洪水ハザードマップ」に掲載されている以外の函館市中央部も対象とされたことから、対象となった地域の多くの企業や店舗は、従業員に一時避難や帰宅を促し、幼稚園や保育園は保護者に連絡して迎えを要請、夏休みに入った小学生達にも不安が広がりました。
西部地区は、これまで何度も津波の被害に遭っており、住民にはその記憶が残っている方も多いですが、この地域は観光地と重なっています。つまり外国人や観光客が何処に避難して良いか分かりませんし、同じく外国語での避難広報が全く不十分となっている事も浮き彫りとなり、駅では誘導する駅員の姿も見えなかったとの声もあります。
一方、市内でも津波に関わる交通規制が敷かれましたが、避難に車を使用する方々が渋滞を招き、警察による交通整理が十分だったとは言えません。ご高齢の方は徒歩での避難となりますが、自力で避難施設へ行けない方は、自宅に閉じこもってしまう事も。
今回は避難場所が学校に集中していましたが、酷暑の中での空調が問題で、簡易的な冷房があっても暑さが緩和されないこと、高齢者施設は垂直避難を実施しましたが、今回はいつもの訓練とは違って本番の対応となり、課題も多かった勝ったようです。
何れにしても、個人を含めてそれぞれが考えてきた危機管理が少し甘く脆弱だったことが浮き彫りになりました。
「災害は忘れないうちにやって来る」ということを踏まえながら、保育・教育機関、高齢者介護施設、医療機関、避難所、交通管制、防災担当行政機関等などは、本番と同様だった今回の経験を様々な角度から検証し、個々人がどのように対処すべきかを深く考えて、「イザ」の時に備えなければなりません。