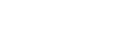米の確保と適正価格(ブログ3926)
- 2025年05月28日
24年産の主食用米の収穫量は、作況が101%で前年より約18万トン多い約679万トンとなりました。
したがって現状を見ると、米はどこかの貯蔵庫などにひっそりと貯め込まれている事になります。
そこに、100万トンの備蓄米がすでに30万トン以上放出され、小泉農水相によって更に30万トンを放出、これで24年産米、23年産米(古米)、22年産米(古古米)が放出されることになり、7月までに21年産米(古古古米)も放出することになります。
備蓄米で一番古い20年産米(古古古古米)も視野に入れているようですが、先般も記載したように、これは飼料米となるはずの米です。
備蓄米が放出されても、国民全ての需要に応える量とはなりませんから、当然どこかにあるはずの昨年産の米が出回ることになりますが、仕入れ価格が高騰したときのブランド米を4,500円以下で売ることは赤字を覚悟することになり、損をしないためにも価格が下がることはないと思います。そうなると、小売り段階でブランド米と放出米の価格の二極化が表出します。
また、今年の25年産新米が収穫されれば、市場にはまた4,000円台の米が並ぶことになります。つまり、放出米はすでに使い果たしていますから、価格調整は難しくなります。所得層によってブレンド米を購入できる層と、そうでない層の格差が現れます。また、米はすぐに増産できるものではありません。そして、備蓄米が無くなってしまえば、本来の大災害や凶作(不作)になった場合に放出する米はありません。小泉氏には、一時的な難局をパッチワークで逃れても、すぐに次の難題が待ち受けます。
さらに、来年の備蓄米は、25年産米の20万トンしか確保出来ず、そこから5年間は備蓄米に手を付けることが出来ません。そうなると次の手は輸入に頼る事になります。
米は生産国の売り手市場になることが懸念されますから、値段はそんなに下がらないことが想定出来ます。なにしろ、米価に関して政府は市場価格に委ねる姿勢を貫いていますから。そして、いったんトランプの米国から米を輸入することになれば、毎年同量以上の輸入を求められるでしょうし、これに「NO」とは言えるはずもありません。
その結果、食糧自給率の向上は難しくなり、今以上に外国に依存することになります。
米の安定供給と適正価格を保つこと、農家の所得向上と後継者対策を両立させること、これが果たして今の政権で可能なのか、国民が安心できる道筋を示すことが何より求められます。