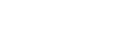米の価格(ブログ3916)
- 2025年05月12日
備蓄米を放出しても、一向に米の値段が下がりません。
値下がりしないだけでは無く、徐々に値上がりしています。
政府は、備蓄米20万トンを放出して市場価格を抑制しようとしていますが、スーパーなどにはなかなか備蓄米が届かず、消費者は「いったいどうなっているのか」と、政府に対して不信の気持ちを抱かざるを得ません。
近年の米生産量は年間約730万トンほど。消費者の米離れや人口減など、これまでの農業計画は減反の方向を強めています。しかし、昨年からの米不足は政府の想定外だったのか、多くの有識者が色々分析がなされていますが、様々な理由が複合的に重なり、現状の米不足と価格の高騰に特効薬がなかなか見つからないという所です。少し前まではコンビニのおにぎりは1個100円で購入できましたが、今は、180円前後になっていますから、手軽にコンビニのおにぎりとは行かなくなったきました。
政府備蓄米は100万トンとされていますが、これは大災害時などの緊急時に人口1,000万人の1年分という基準で備蓄されています。この基準も日本の人口が1億2,000万人なのに、なぜ、こんな基準なのか、いささか納得がいきませんが、100万トンの備蓄米は、毎年20万トンを入れ替える事になっています。これを全部放出すると5年前の米も入ってしまいますから、食味を含めても現実的では無いと思います。新しい備蓄米が入荷されると5年前の米を飼料米や海外への支援米などに回すことになります。
従って、食用として放出できるのは3年前までの60万トンがギリギリと言う事でしょうか。政府は今後、新米が収穫されるまでにどれだけの備蓄米を刻みながら放出していくことで、安心感を持って貰えるのか手探りながら行っていくことになるものと思います。
(まだ、60万トンを放出するとは決まっておりませんが)
更に、備蓄米をJA等の集荷業者に売り渡す入札の参加条件として、「原則として売り渡してから1年以内に政府が買い戻す」事になっています。つまり、集荷業者は入札した分を政府に売り返さ無ければならないと言う事です。これは、政府が備蓄米を常に100万トン用意しておかなければならないからですが、集荷業者は、今年秋の収穫後に農家から従来の集荷量以外に備蓄米入札分も確保出来るかが見通せないことから、集荷業者の入札のハードルとなっていることから、政府はこの1年間という期間を延長することを検討しており、江藤農水相も制度を改善する考えを示しました。いずれにしても、早急に改善して欲しいと思います。
さて、夏までに順次放出量を増えたとして、さらに集荷業者が政府に売り返す期間が延長されたとしても、米の価格が下がるかというと流通はそうはいかず、なかなか手強いようです。それは、備蓄米が放出されても、備蓄米以外の米の仕入れ価格に大きな変化が無ければ、なかなか値下げに結びつかないと言うことです。
また、一度米不足を経験すると、不安のマインドはそう簡単に解消すること無く、集荷業者から仕入れ業者、スーパー、コンビニ業界、デイリー産業までも、「根本的に米の生産量が足りていないという現状も含め、そこが改善されなければ、市場の不安を払拭する事が出来ない」という懸念もあり、価格に反映するまでに至りません。
トランプ減税の交渉で、日本が米国米の輸入を取引に使うとも言われていますし、日本のブランド米を世界に輸出することも相まって、今後の米政策をどのように展開していくのか、政府の責任は非常に重いものだと思います。