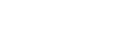注目の第4回定例道議会(ブログ4106)
- 2025年11月27日
副知事が25日、自民党会派のエネルギーに関する会合において「現実的な選択肢として再稼働はやむを得ない」という鈴木知事の意向を説明したことが報道され「28日の代表格質問に答える形で再稼働を容認するのでは無いか」という活字が、驚きを呼びました。
道は自民党会派への説明した26日にも、他の会派には一切の説明がありませんでした。
そんな中、25日は午後からエネ特(産炭地域振興・GX推進・エネルギー調査特別委員会)が開催され、その中で、自民党以外の委員から泊原発に係わる質問が有りましたが、その時の答弁は、これまでのように「地域の声や、道議会の議論などを総合的に判断したい」と答えました。既にこれ以前に自民党へは鈴木知事の意向を話したにもかかわらず、公式の委員会では、従前の答弁を繰り返したことが問題となり、翌日の本会議開会日に、質問を行った会派が「副知事の説明もない中で、会派の委員のエネ特での質問が軽視された。このような議会軽視の中で本会議は開催できない」という主旨の主張を行い、本会議開会が1時間以上遅れる事態となりました。
我が会派も同様に「道の説明が、会派によって区別されるとは容認しがたい。副知事が3人もいる中で、手分けをして対応する事は可能にも係わらず、自民党以外の会派には説明さえしないという道の姿勢に憤りを覚える」として、副知事の説明を求めました。
この中で副知事は「今日段階の状況を説明しただけで、最終判断を示したわけでは無い」と説明、その後、本会議は開催されましたが、予断を許さない定例会となりそうです。
自民党は、一部強行に再稼働を求めるベテラン議員がおり、多くの議員はそれに追随するような形で、会派として容認する方向となったようです。
さて、報道では知事の容認する理由として、 ①電力需要が今後増える見通し ②二酸化炭素を減らすため ③北電が再稼働した場合の電気料金の値下げ幅を示しました。
これが最大の理由と考えているようです。しかし、
①の電気需要が増えるという理由は、OCCTO(オクト:電力広域的運営推進機関)の推計のみを丸呑みしていますが、道は人口が減少しており、個人および輸送関連の電気需要は減少傾向にある事、「北海道省エネルギー・新エネルギー促進計画」によって省電力家電や高断熱住宅・ビルが計画以上に取り入れられていること、北海道は再生可能エネルギーの賦存量が全国的に高く、今後も、海洋風力発電の促進区域認定によって、膨大な電力が生み出されること、何より「北海道省エネ・新エネ促進条例」では、「原発は過渡的なエネルギー」と位置づけており、脱原発の方向性を明らかにしていること。
半導体やDC(データーセンター)の誘致により電力が増大するというのは詭弁で、ラピダスは電力を自前で用意する事になっており、苫小牧に進出する「ソフトバンクDC苫小牧」も自前で、石狩湾新港に進出の「さくらDC」も風力発電を利用することとなっており、IT関連企業は再生可能エネルギーにシフトしていますので、電力の増加は単なるプロパガンダ的な情報操作でしか無いと思います。
②ついては、まさしく再生可能エネルギーや、水素、地熱、バイオなどの新エネルギーを推進する事で、CO2は排出されず、既にドイツやイタリアでは原発が動いていないという前例もあります。
③については、北電のこれまでの電気料金は、国内で最高値であったことから値下げは当然のことであり、再稼働後に値下げを行っても他の電気事業者と比較して高い値段である事に変わりが無い事、北電の内部努力も値下げに寄与するとのことですが、それでは、今まで内部努力を怠っていたということになるのではないでしょうか。
議会の連合審査でも、エネ庁は北海道の省エネルギー対策について高い評価を行っていること、半導体やDCの電力事情も分かっていること、北海道は再生可能エネルギーの宝庫であって、今後もそのポテンシャルを北本連携線も含めて日本のエネルギーの安全保障を担ってくれる地域であることを認めた上で、政府のエネルギー比率の2割が原発だと話しています。単に政府の立場から、エネルギーは充足されていても原発を稼働させて欲しいというニュアンスで話していました。
また、鈴木知事は、肝心の道民に意識調査もせず、安全対策にも触れずにいます。
つまり、道民には「危険かも知れないけど食べて欲しい」、「安心では無いけど食べて欲しい」と言っているに等しいのでは無いでしょうか。
まだまだ、問題点の多い泊再稼働について、今後も議会の場で追求して参ります。