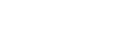泊3号炉合格?(ブログ3906)
- 2025年05月01日
原子力規制委員会が30日、泊3号機の安全対策が安全基準に適合していると判断し審査書案を了承しました。これによって規制委員会の審査が終了し、事実上再稼働について合格したこと認めました。
今後は、今日から30日間のパブリックコメントが行われ、経産省と原子力委員会への意見徴収を行った上で、今夏にも再稼働に対する地元同意を要請することになります。
地元とは、北海道及び原発立地4町村である泊村、共和町、岩内町、神恵内町(北電と安全協定を結んでいる自治体)で、知事も4町村の首長も今の段階での再稼働の賛否について明言を避けています。
鈴木知事は、これまでの道議会において、「原発は、安全が第一」と繰り返して答弁しています。
一方、北電の斉藤晋社長は「事故が100%無いというものは世の中に無いと思っている」と発言しており、規制委の中山委員長も「新規制基準の適合性が認められても100%の安全を保証するものではない」と話しています。
つまり、原発を運転管理する北電も、安全を審査する規制委も100%の安全は無いということです。原発に対する二人の責任者が、この期に及んでも100%の安全は無いとして、事故が生じた時の責任を回避しています。フクシマ第1原発事故の原因にあたっても、東電の責任者は「想定外だった」と言い訳をしましたが、想定外は想定されるのです
この原発事故の検証が多く行われましたが、経産省も、東電も、当時の原子力委員会も、つまり誰も事故に対する責任を負わない事だけが明らかになりました。
泊原発3号機の再稼働も事故に対して誰も責任を負おうとしない旧態依然の認識が示された事は非常に残念です。北電と規制委、そして経産省が言わなければならないのは「100%の安全は難しいが、仮に事故があった場合の責任は“北電が”、“規制委が”、“経産省が”責任を負います。」と言わなければなりません。それが国策として原発を進めている政府、安全を科学的知見で審査した規制委、運転管理を担う北電の覚悟では無いでしょうか。今回の国電、規制委の言葉を聞いても道民に対する覚悟が全く感じられませんし、
関係責任者全てが「逃げを打っている」姿しか私たちには映りません。
さて、柏崎刈羽原発は、新潟県中越地震による想定外の揺れによって変圧器の火災や敷地内道路の陥没が起き、それ以後、大きなトラブルが4回発生、今も緊急時の衛星通信の問題が4度も起きていますが、解決さえしておらず規制委の追加審査を受けており、新潟県知事はこれまでも原発の再稼働を認めておりません。また、昨年1月の能登半島地震では、半島沿岸の海底活断層が従来の想定を超えて広範囲に連動、休炉中ではありましたが志賀原発では、敷地中央部の道路が沈下、護岸との間に35cmの段差が発生、使用済み核燃料プール冷却浄化系ポンプが停止、起動変圧器から3600リットルの絶縁油の漏れ等、合わせて17ヶ所のトラブルが発生しました。この志賀原発については23年3月に規制委が活断層は無いとの審査内容を発表しましたが、能登半島地震の活断層は100km以上有り、海底活断層150km以上にズレが生じていたことが分かりました。
原発は、一度事故があれば多くの犠牲者を生み、自然環境の大規模破壊を誘発し、放射能による長期間の影響をもたらします。
100%の安全以上に150%の安全、いや完全なる安全が無い限り、手を染めるべきでは無いのです。