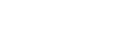日本手話による授業(ブログ4036)
- 2025年09月15日
「『日本手話』での授業を受けられないのは違法で、教育を受ける権利をを侵害された」として道に賠償を求めた裁判で、札幌高裁は地裁判決を支持し、「日本手話で授業を受ける権利は法令で具体的に規定されていない」と原告側の訴えを棄却しました。
憲法26条第1項では「全ての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する」、第2項では「全ての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする」としています。
つまり対象子女には教育を受ける権利を、そして行政には教育を提供する義務をについて規定しています。
にも関わらず、司法が「日本手話は法令で具体的に規定されていない」として、原告の主張を棄却するのは納得がいきません。
保護者は、「とても苦しい判決になった。障害により情報を受け取れない責任は、児童たちにあると言いたいのかと感じた」と話し、原告代理人の弁護士は、控訴するかについては今後検討すると話しています。
一方、斉藤裁判長はが「日本手話」での教育が受けられるように法を整備すべきと言うことを付け加えました。斉藤裁判長は「教員との意思疎通を欠くことになれば、成長発達期の児童の心身の負担も重くなり、聾学校には課題もある」と付言し、「障がいを抱えた児童に適切な配慮を尽くし、学習意欲を持続させる努力を続けることを望む」、詰まり、原告のような立場のこども達にも教育の機会を与えるべきとの考え方も示しています。
「手話施策推進法」は、第2条基本理念に「手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに合理的配慮が適切に行われるために環境の整備が図られるようにすること」と記されていますし、第7条では国及び地方公共団体に「手話を使用するこどもが在学する学校において、その意向ができる限り尊重されつつ手話による教育を受ける事ができるよう、手話の技能を有する教員、手話通訳を行う者、手話に関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるようにするための取り組みの推進」を求めています。
また、「北海道障がい者の意思疎通の総合的な支援に関する条例」の第3条基本理念では「意思疎通に支障が生じている障がい者が多様な意思疎通手段を使用し円滑に意思疎通を行えるよう、障がいの特性に応じて総合的に推進しなければならない」と規定。
無論、法にも条例にも、そのための財政上の措置を講じることも記載されています。
道教委の中島教育長は「この度の判決では、当方の主張が認められたものと考えている。引き続き、日本手話を含む手話を適切に活用しながら、学習指導要綱に基づく教育活動をいっそう努めていく」とコメントしました。
今回の訴訟は損害賠償という事が争われましたが、本来は、「日本手話」での授業が受けられる権利を保障することです。裁判長の言うとおり、法の不作為が原因であれば、国会において法の整備を図るべきですし、法が整備される前でも条例がそれを補うことは出来るはずですし、超党派で作り上げた道の条例についても、今後、道議会で協議が必要と思います。