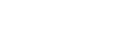やらせ質問(ブログ3893)
- 2025年04月18日
苫小牧市議会をはじめとする議会の「やらせ質問」のアンケートを道新が行った結果、人口10万人以上の12の市議会で、議員の質問を職員が作成した事実は無いと言うことが、公式の回答として有ったようです。
アンケートでは「市側が議会側に質問を作成させて欲しいと求めたり、議会側から求められたりした事はあるか」という問いに対し、10の市と11の議会が「ない」と回答、双方が分からないと回答したのは小樽市と小樽市議会。「聞いたことがある」と回答したのは苫小牧市でした(この期に及んでも、苫小牧は事実を認めない)。。
しかし、匿名で複数の職員や市議への取材では、苫小牧、帯広、室蘭、札幌、旭川、北見、釧路、小樽、千歳の9市議会と道議会で類似の事例が現在もある、または過去にあったという証言を得た事も掲載されていました。
ここでも行政のアンケートは真実を表していないことが分かります。いえ、真実を語る事による影響を市も議会も気にして本当のことを言えないのだと思います。
函館市はやらせ質問は無いと回答しましたが、私が函館市の職員に取材した結果、「それは表だって有ったとは言えないけれど、函館市議会も職員に質問を作成させる事実は有る。」と答えてくれました。
事実、私が函館市議会議員をしていた11年間で、同じような事に触れたことは幾度となくありました。それも与党や与党に近い議員です。そして、一度職員に質問を頼むと当然の様に次も次もと習慣的になってしまうようです。
職員は所管する行政の「スペシャリスト」です。一方、議員は、全ての行政に目配せしなければならない「ゼネラリスト」です。当然、当該案件の情報量と知識の深さでは職員に適いません。市長や部長・課長(理事者)の答弁の裏には、所属する部・課の職員が全員後ろにいますが、議員の場合は一人で問題点を調査し裏付けを整え、自身の主張の正しさを信じて、議会において理事者に質問します。
本会議や委員会での質問をするためには、その案件の調査と原稿作りに多くの時間を費やす事になります。逆に質問しなければ、非常に楽であると言うことです。
しかし、ずーっと質問しなければ支持者が離れていくことも気になりますから、たまに質問をしようと考えますが、その方は、何を調査すれば良いのか、原稿をどのようにまとめていくか、非常に不慣れであることから、誰かに頼ります。それが職員と言うことになります。
道議会も同様ですが、期が重なっていく度に質問の機会は少なくなっていきます。それは、期の若い方を優先するという慣例も影響していることは否めません。
私はその中にあって、できる限り質問の機会を得るようにしています。
そして、本会議では再質問・再再質問・特別発言まで行ってきました。委員会や特別委員会でも、予告している質問趣旨と異なる質問もしますし、相手の答弁によって柔軟にディベートもします。
残念なことに、道議会の与党会派の方々は、本会議で再質問は当然、再再質問もせず、最初の本質問だけで終了します。そのためには綿密な打ち合わせが必要なのかも知れませんし、慣れない案件ではスペシャリストである職員に頼るのが一番と思ってしまう議員も出てきます。一方、期の若い方々は、本質問だけでは絶対に不満が溜まると思います。
そのために知事が出席する本会議での一問一答制(一つの課題について何度も質問をする事が出来る制度)の導入を、道議会議員になってからずーっと主張してきましたが、与党の反対で未だに実現しないのです。議会改革に後ろ向きな議長と議運委員長が続いている限り、何も変わりませんし、これからも、やらせ質問は行っていないと公式に答えながら、内実はそれと違う事が続いて行くだろうと思います。
私たちが議会で質問を聞いていると、これは「やらせ質問」だと言うことが分かります。
やらせ質問は議員の資質を低下させてしまうものですが、理事者にしてみれば、議員を手の平に置いておくことが、肝要なのかもしれません。