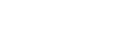道主催の説明会(ブログ4022)
- 2025年09月01日
昨日のブログで、北電の住民説明会のことを指摘しましたが、今度は、北海道としての説明会を開催することになりました。
道主催の住民説明会は、これまで私たちが求めていたことですから、そのことを道が受け止めたことは評価します。
報道によると、その説明会の進め方ですが、国や北電の担当者を招き泊原発の安全対策などの付いて説明を求める予定とのことのようですが、これは、私たちの求めていた内容とは似て非なるものです。
北電の説明会の二番煎じを道が行って何の意味があるのでしょうか。そんな説明会なら実施する必要性は全くありません。また、参加する住民も同じ話を2回聞くことになりますから、時間の無駄ですし参加者も少ないでしょう。
北海道が行う説明会は、再稼働に対して住民がどのような意見を持っているのか、その事を参考にするための説明会でなくては意味をもちません。
既に北電の説明会で一方的な安全論を聞かされたのですから、道は公平な立場で推進側の北電の陳述者と反対の立場の専門家など双方に意見と討論をして貰い、参加者からも双方への質問も行って、入場時に渡していたアンケートに<賛成>、<反対>、<どちらとも言えない>、出来れば、意見も書いて貰い、閉会後に集める。当然、その会場に道の担当職員も出席して、会場の雰囲気などを受け止めてもらう、当然、過去のような北電の関係者が「サクラ」となって出席したり、賛成意見を述べて住民を誘導したりすれば、北電にとっての致命傷となるだけですから、そのことは改めて北電に釘を刺しておくべきだと思います。
開催する地域は、北電がおよそ30ヶ所を予定している事から、北海道は最低でも関係自治体・後志管内とUPZ圏内の自治体、加えて14振興局管内で開催することが、道民の声を公平に聞くことだろうと思いますし、当然UPZ管内と避難先の首長の意見を聞くことも必要となってきます。
知事の政治姿勢は、道民の声を生で聴く<直道カフェ>や、自治体首長との意見交換を行う<スクラムトーク>では無かったかと思います。
道民にとって、とても重要な泊三号炉の再稼働の是非についての判断です。
より慎重に住民説明会を行うべきでは無いのでしょうか。