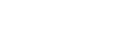概算要求基準(ブログ4012)
- 2025年08月22日
26年度の当初予算編成の基本方針となる「概算要求基準」を閣議で了承しました。
概算要求基準は歳出の際限ない増加を防ぐため、歳出抑制を基本としてきましたが、ここ数年の間に形骸化が進み、今回の基準でも重要政策に充てる「裁量的経費」については25年度予算の2割増での要望を可能にしました。
政府予算は、19年度に初めて当初ベースで100兆円を突破し、その後は、コロナ対応などで膨らみ続け、25年度は115兆円となりました。
当然、これは当初予算ベースですが、年度途中に補正予算を数兆円規模で増額していますから、最終的には決算を見なければ年度の歳出は明らかになりません。
この間、税収は増額しているものの、幾度となく給付金などの名目でバラマキを行ってきていますから、赤字国債の発行もその都度増え続け、国と地方を合わせた長期債務残高は24年度末で約1,300兆円となっており、依然として先進国で最悪の水準となっていますし、日銀も再び利上げを行う考えのようで、利上げによる国債の利払いの増加も見込まれます。
一方、国民の暮らしは物価高の中で苦しい生活を余儀なくされていますから、これの対応も必要となってきます。参議院選挙では、野党だけでは無く与党もガソリンの暫定税率の廃止に舵を切りましたから、年内には実現するかも知れませんし、少数与党の悲哀から消費税の減税にも何らかの方向性を出さなければなりません。
しかし、暫定税率についても消費税についても、その一部が地方財源に充てられていることから、政府としてもその財源を確保しなければ、地方が割を食い、その結果住民サービスの低下というツケが国民にまわってきますし、後年度負担は若年層にのしかかります。
さらに、人口減少や少子高齢化という喫緊の課題にも対処が求められますし、防衛費GDP2%への増額などの歳出増が目の前に迫っています。
足下の政策だけでは無く、将来を見据えた責任のある予算編成が求められますから、与党だけでは無く野党も財源の在り方についてのビジョンを示す必要があると思います。