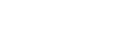北電による説明会(ブログ4021)
- 2025年08月31日
3号炉再稼働に関する北電主催の住民説明会が、先ずは安全協定を結んでいる4町村から始まりました。
その後は後志管内の19市町村、そして、北電の支社等がある道内9市で開催します。
説明が行われた4町村では、泊原発の安全性や必要性について北電から話され、新港についても話されました。
北電が開催する説明会ですから、「規制委から基準に適合するという判断をいただいたので、安全である」と言うことを全面に出して答えるであろうことは、説明会に行かなくても想定出来るものですし、必要性についても「ラピダス社やデーターセンター(DC)を引き合いに出して、今後は電気需要が増大するのでCO2を排出しない原発が不可欠」と説明するでしょう。
説明会に来た住民は、「なるほど」と思って会場を後にするでしょうし、それをもって北電は住民理解を得たと評価するでしょう。
原発の再稼働については、専門的知識がなければ疑問点を指摘することは難しいと思いますし、仮に疑問点を指摘しても、相手は原発の専門家ですので、うまく言いくるめられてしまいます。
泊原発は、原子炉建屋は岩盤の上に建設されていますが、付帯施設は埋め立て地に建設されています。また、海底活断層の長さや位置についての能登半島地震の検証、火山活動については270万年前以降の第4紀に噴火した火山灰が新たに発見されたことも、規制委は新知見として検討を行っていません。学会が査読付論文と認めていてもです。
また、原発の運転を経験していない職員が相当数いますが、この問題については他の原発に派遣して運転技術を継承していると言いますが、事故が起きた場合の対処は、その時の状況によって大きく変化し、それに対して適宜最善の対処をしなければなりません。
福島第1原発事故でも、その場で判断して指示を出したのは吉田所長一人だけでした。
北電泊原発に関わる運転員が、運転だけでは無く事故への対処に十分なスキルを持っているかは疑問です。机上の研修だけでは突発事故に対処できるとは思えません。
消防職員でも、消防学校での研修だけでは無く、実際の火事現場で先輩から身体でノウハウを学びます。しかし、原発だけは机上の研修だけしかできません。事故現場を再現できないからです。
また、住民の避難は犠牲者を出さずに実行できるのでしょうか。この問いに対して、行政も北電も「最善を尽くす」としか答えられないはずです。
規制委の中山委員長も規制委として安全基準に適合していることは言えても、「安全については言えない」と発言し、北電の斉藤社長も「100%の安全はこの世に無い」と開き直っていますが、原発は100%安全で無ければ運転すべきでは無いのです。
さらに、原発を稼働させれば、使用済み核燃料が発生します。現在の日本では核燃サイクルが破綻していますから、高レベル放射性廃棄物では無く使用済み核燃料の廃棄場所が必要となっていますが、この廃棄場所も決まっていません。仮に決まっても建設して使用出来るまで永い歳月が必要となってきます。そうなれば、使用済み核燃料は、泊原発に中間貯蔵しなければなりません。その計画も北電には無いのです。
CO2を排出しないから環境に負荷をかけないと言いますが、常に使用済み核燃料が側にあると言う精神的負荷は大きなものですし、もちろん貯蔵施設に事故が無いとは言いきれません。
これらの課題を、私たちが納得出来る様に説明して欲しいと思います。